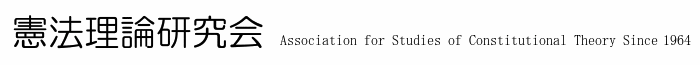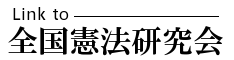初代代表 鈴木安蔵のこと
憲法理論研究会の創始者・鈴木安蔵氏の人と学問
金子 勝(立正大学法学部教授)
憲法理論研究会は、鈴木安蔵の提唱により、1964年1月11日に、東京(勁草書房2階応接室)で創立された。初代の代表となり、草創期の憲理研を主導した鈴木安蔵は、1904年3月3日、福島県相馬郡小高町(現・福島県南相馬市小高区)で生まれた
鈴木と憲法学を結びつけた直接の動機は、鈴木が治安維持法の犠牲者となったことにある。治安維持法(1925年4月22日公布)は、「国体」(天皇を中心とする国家体制)及び私有財産制度を否定する思想と運動を弾圧する法律であった(1928年6月29日改正で死刑・無期刑が追加された)
福島県立相馬中学校(5年制)を4年で修了して、1921年4月に旧制第二高等学校(仙台)に入学した鈴木は、2年生になった時、ロマン・ローラン『ジャンクリストフ』に眠らぬ感激の夜をもったと語った新入生の栗原佑(京都出身)を心からうらやみ、彼に刺激されて目茶苦茶な乱読を始めた。その乱読のなかから、鈴木は、当時流行のドイツの哲学者、ヴィンデルバントやリッケルトの提唱する新カント主義哲学、また、西田幾太郎の西田哲学に熱中する哲学青年となっていった。いたるところで学生に論争をふっかけるところから、「新カント主義哲学の鈴木」として校内で鳴らした。
その旧制二高時代、2年生の鈴木は、親友となった栗原から、関西地方での労働運動や社会主義運動の展開のことを知り、社会問題に目覚めた。そして、1923年の関東大震災後の秋に、貧困、飢餓、失業、売淫などの矛盾を除去するため、真剣に自己と社会との進路を求めるという意図をもって、栗原ら20余名とともに、二高社会思想研究会を結成した。この活動から、鈴木の頭脳にマルクス主義の影が宿った。
鈴木は、読書の影響から、文学者となるか哲学者となるかで迷った末、哲学を研究しようと決意し、1924年4月、京都帝国大学文学部哲学科に入学した。直ちに、マルクス主義の研究と普及・無産者教育への貢献を目的とする学生の思想研究団体である京都帝国大学社会科学研究会(京大社研)に入会する。鈴木は、1年生の時、講義を1日も休まずに聴く一方、京大社研の研究会で、ブハーリン、マルクス、エンゲルス、レーニン、スターリンなどの文献を読んでいく。が、マルクス主義を本格的に学ぶにつれて、マルクス主義(弁証法的唯物論及び史的唯物論)と新カント主義(観念論)の矛盾に悩むことになる。その苦悩のなかから、鈴木は、現代社会の汚辱を一掃しようとするかに見えるマルクス主義こそ、社会の矛盾を除去したいと考えるわが魂の救いではないかと考えるに至り、ついに、マルクス主義の研究に本格的に取り組むことを決意する。
マルクス主義の研究一途を決意すると、鈴木は、象牙の塔のなかで哲学をやっていたのでは駄目だ、経済学を学び、『資本論』を学び、「人民の中へ」行かなければならないとの気持ちから、周囲の助言を振り切って、1925年4月、経済学部に転部した。
経済学部に移って、「人民の解放に役立つ理論と実践を」との考えのもと、鈴木は、マルクス主義理論の研究や、京大社研と労働組合・農民組合との連携によって設置された「無産者教育」の講師などの実践に熱中する。そのさなかの1926年1月18日、鈴木は、仲間と共に、治安維持法第2条違反容疑で逮捕された。最初の治安維持法違反事件としての「日本学生社会科学連合会事件(学連事件)」である。
京都地裁は、1927年5月30日、全被告を8カ月から1年の禁固刑に処す有罪判決を出した。鈴木は、禁錮10月だった。すぐに控訴するも、大阪控訴院は禁錮2年に量刑を引き上げ(1929年12月12日)、大審院に上告するが棄却され、有罪判決が確定した(1930年5月27日)。マルクス主義の文献を研究したことが、また、「ヴ・ナロード」(人民の中へ)の気持ち(正義感)で行動したことが、国法上の犯罪になるということは、鈴木にとって、大きいショックであった。
鈴木は、一審判決直後に、京都帝国大学を自主退学し、また、結婚し(1927年6月16日、栗原俊子と)、大学の外で、自分たちを処罰した天皇制国家の本質を解明すべく、憲法学・政治学の研究に取り組むことを決意する。鈴木は、1929年2月から、東京で憲法学・政治学の研究を始めるが、「第二無産者新聞」に執筆したことなどが治安維持法に違反するとして逮捕された(1929年10月21日)。こうして、「学連事件」の有罪判決の執行も加わって、鈴木は、1932年6月17日まで、市ヶ谷刑務所(後に豊多摩刑務所)に収監された。
獄中で、鈴木は、俊子夫人の差し入れを介して、憲法学者の著書をほぼ余すところなく読み、日本の憲法学には、憲法の成立過程の研究がないこと、また、憲法理論批判がないことに気づく。そして、憲法の歴史的研究と憲法理論批判をマルクス主義の方法で行うという研究プランをまとめる。それは、憲法の歴史的研究(憲法史研究、比較憲法史研究、憲法思想史研究、憲法学史研究)が行われないと、「学連事件」で自分たちを処罰した「国体」の本質を解明することができない、憲法理論批判が学問化されないと、「国体」を科学的に批判することができない、しかも、それらの研究の科学性を担保するにはマルクス主義の方法によることが必要である、という考えに鈴木が到達したことにある。
出獄後の1932年9月から、鈴木は「研究プラン」の実現に着手し、呻吟のなかで、マルクス・エンゲルスの著作、クルイレンコやスタリゲヴィッチのソ連法学文献から理論的示唆を受け、また、吉野作造から直接の指導(1933年1月8日、3月5日)を受けて、ついに、鈴木にとっても、また日本憲法学にとっても記念碑的な著作となった『憲法の歴史的研究』(大畑書店、1933年6月20日)を発刊するに至った。だが、これは即日、発売禁止処分を受ける。
この書物は、フランス諸憲法(1791憲法からパリ・コミューン憲法まで)と1850年のプロシア憲法の歴史的分析(比較憲法史的研究)を行った第1篇と、大日本帝国憲法制定史の考察(憲法思想史・理論史的研究)を行った第2篇、そして、諸憲法学者の憲法概念(学説)の歴史的変遷を批判的に検討した憲法学史研究と憲政批判(憲法理論批判)を行った第3篇より成る。ここには、以後の鈴木の研究活動のスタイルの原型と研究の方向が散りばめられていた。この『憲法の歴史的研究』は鈴木憲法学の成立を画する重要な著作となった。
鈴木憲法学の成立の意義は、第1に、日本における「マルクス主義憲法学」の分野が開拓されたという点にある。このことは、日本憲法学のなかに、初めて、民衆の立場に立った憲法学が生まれたことを意味する。憲法現象の生成、変化、発展、死滅の運動法則を解明できる憲法学が成立したことをも意味する。第2に、日本における「憲法の歴史的研究」の分野が開拓されたことである。このことは、日本憲法学が、歴史学から独立性を確保し、憲法規範と憲法理論の発展法則を明らかにできる憲法学になったことを意味する。第3に、日本における「憲法学批判」の分野が開拓されたことである。このことは、日本憲法学が、現実の憲法体制と憲法政治の本質を解明し、それを貫く発展法則を明らかにできる憲法学となったことを意味する。
こうして、日本の憲法学は、解釈術学から脱却して、研究対象である憲法現象の全体像とそれを貫く発展法則を明らかにできる社会科学としての資格を確保するに至った。従って、鈴木によって、日本における「社会科学としての憲法学」が創始された。
《編集部注》
筆者の金子勝氏は、愛知大学教授時代の鈴木安蔵の門下生である。なお、鈴木は、日本憲法の制定についての研究は、自由民権運動の本格的な再検討が必要であるとの考えから、高知に赴き(1936年5月29日~6月2日)、自由民権運動期の私擬憲法を発掘し、自由民権運動の研究にも取り組む。鈴木は1939年、土佐の植木枝盛の「東洋大日本国国憲按」の発掘とその分析を憲法史の本で公表している。
戦後すぐ、鈴木は、高野岩三郎や森戸辰男、室伏高信らと7人で民間の「憲法研究会」を創設(1945年11月5日)。鈴木が起草した「憲法草案要綱」(同年12月26日発表)は、植木枝盛ら自由民権運動の私擬憲法も参考にしていた。「憲法草案要綱」はGHQに届けられ、日本国憲法の起草過程に重要なヒントを与えることになった。特に象徴天皇制というアイデアは、植木が「皇帝」の権限に対して「立法院」の同意を随所にセットして、実質権限を議会に委ねようとした、さまざまな憲法的工夫と響き合う。家永三郎は、『植木枝盛選集』(岩波文庫)の解説で、日本国憲法の原案となったマッカーサー草案の作成にあたり、占領軍は、戦前におけるほとんど唯一の植木枝盛研究者だった鈴木安蔵が起草した「憲法草案要綱」を参考にしたことを指摘して、「日本国憲法と植木枝盛草案の酷似は、単なる偶然の一致ではなくて、実質的なつながりを有する」(322頁)と書いている。日本国憲法には、鈴木安蔵を通じて、自由民権運動と植木の憲法構想が息づいている(水島朝穂HP『平和憲法のメッセージ』内「「世に単によい政府なし」(植木枝盛)2000年12月25日」に移動します)。
その後、鈴木は1952年に静岡大学教授となり、愛知大学教授、さらに立正大学教授に就任する。憲法理論研究会の代表を19年間務め、1983年8月7日、79歳で死去した。
《補注》水島朝穂「憲法理論研究会と鈴木安蔵のこと」(「直言」2012年11月5日)