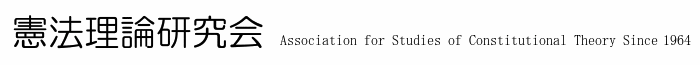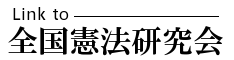憲理研の思い出
憲理研創設の頃 永井憲一(法政大学名誉教授)
憲法理論研究会の草創期の想い出 吉田善明(明治大学名誉教授)
草創期憲理研の記憶 樋口陽一(東京大学、東北大学名誉教授)
ホームグラウンドとしての憲理研 辻村みよ子(東北大学大学院法学研究科教授)
憲理研創設の頃
永井憲一(法政大学名誉教授)
主題について書くように、との水島朝穂代表からの依頼があった。でも、もう50年も前のこと。記憶の曖昧な点も多いが、想い出す範囲のことを書き留める。
憲理研は、1964年1月11日に結成された。事の起りは、60年代初期、京都大学で公法学会が開催された夜に開かれた、『政治学研究叢書』(勁草書房)の執筆者の会合であった。その席で鈴木安蔵先生は、「いまや近年の政府の改憲動向をチェックする憲法学者集団の結成が必要だ」と強調された。それが契機となって、同志の集まる気運が生まれた。
早速、鈴木先生と日常親交のあった小林孝輔、星野安三郎の両先生が、鈴木先生を代表とする集団づくりに動き始めた。結成までの代表を鈴木先生が引き受けることになり、会合に列席した黒田了一、一円一億といった諸先生方も会員となった。
その会合に参加していた僕にも、鈴木先生から、若手研究者集団の結成の原動力となるようにとの要請があった。そして、東大に内地留学中だった、先生の門下生の影山日出弥さん、東北大学で先生の後輩に当たる針生誠吉さん、そして東大大学院生だった隅野隆徳さんの計4人に準備が委託された。この4人が、憲理研創設時の第1期事務局となった。
まず会員となる若手研究者を集めるため、主に青山学院大学の法学研究室を活用して継続的な研究会を開いた。ここに早くから参加されたのが、清水睦、佐藤司、山崎真秀、野中俊彦、岩間昭道の各氏である。短期間に、意外に多数の研究者が集まった。
次に、憲理研を立ち上げるには、全国的規模の組織になることが必要ということになった。そこで注目したのが、当時、関西で田畑忍先生を中心に組織的な研究活動を継続していた憲法研究所との合流であった。そのために僕は縷々西下して、当時の事務局長級の上田勝美さんや有力会員だった土井多賀子さん達とお会いし、その交渉に成功した。
かくして憲理研は結成された。主に弁護士が中心となっていた日本民主法律家協会(略称・日民協)の憲法委員会とも密接な関係をもち、それが内閣憲法調査会の動向を批判する「今日の憲法問題」(『労働法律旬報』505号、1963年11月上旬号の特集)を発表した際、執筆していたメンバーがゴッソリ憲理研の当初会員となった。
憲理研の創設直後、全国憲法研究会(全国憲)が結成され、針生、隅野の両人がその事務局員に引き抜かれた。僕も当初は会員の拡大を目的として参加したのだが、次第に当時の教科書裁判運動の訴訟対策委員会事務局長などを務めるようになっていて、憲理研事務局から事実上離れるようになっていた。そうなると影山さん一人の負担が重くなり、彼は憲理研創設後に入会した大須賀明さん、吉田善明さんと第2次の事務局を編成し、大須賀さんが事務局長となった。多分、1966年頃だったと思う。
そうかといって、憲理研と全国憲とが不仲になっていたわけではなかった。1977年に刊行された『文献選集 日本国憲法』(三省堂)の各巻の編者には、両者から偏りなく編者が出ていたし、憲理研は独自の研究会を継続的に行っていた。
そのなかでも忘れられないのは、第1回の水上合宿のことである。憲理研初期の頃の家族同伴合宿について、鈴木先生は、「これからの憲理研は今日の改憲状況と正面から対決する実践的な憲法理論を創造していく集団となるのだから、政府から弾圧を受ける危険を伴うので、それに向けて平素から家族同士が援助し合える関係を作っておくことが必要だ」と語っていた。家族合宿は2 回か3 回行われたが、その後いつ、どこで行われたかなどについては明確な記憶がない。
やがて憲理研は、会員200 人を超える大所帯となり、創始者の鈴木先生も認めるように、多種、多様な発展をみせるようになった。
主題からは少し外れるが、創設当時の憲理研はどのような活動をし、それと僕はどう関わって来たのかについて、若干触れておきたい。
憲理研創設の頃、こんな政治的背景があった。1951年にサンフランシスコ条約および日米安保条約が締結され、アメリカから日本に憲法を改正して軍備を持てる国としてほしいという改憲要求が強くあった。1953年10月30日の池田・ロバートソン会談において、「教育と広報とにより、国民に愛国心と自衛の精神を植えつけさせることに日本政府が責任を持つ」という解釈改憲の方途が選ばれた。そして1965年、文部省は「期待される人間像」を公表し、教科書検定を強化した。過去の戦争を暗く表現し過ぎているという理由で、家永教科書(高校用『新日本史』三省堂)を不合格にするなど、国民の意識改変を試みる教育政策・行政が強行されてきた。このような改憲動向に対して、国民の側で反対運動が展開され、「教科書裁判」(家永訴訟と呼ばれた)の支援運動もその一つだった。前述したように僕も、その運動に没頭していた。それは、憲理研が創設初期に標榜していた「社会科学としての憲法学」、つまり、従前のような密室的な憲法解釈学の枠を超えた課題と方法を追求しようとしたからにほかならない。
そこで確信し、提唱したのが「主権者教育権論」であった。ここで詳述する余裕はないが、一口で言えば、憲法26条は、『注解日本国憲法』(有斐閣)などにあるような、単なる就学無償を国民に保障したものにとどまらず(修学無償説)、すべての国民が教育を受け、平和で文化的な国の主権者となることを国民の権利として保障したものである、というものだった。同じような論理が星野安三郎さんの提唱する平和的生存権論であった。
この両論は「教科書裁判」の支援運動の中にも遍く活用され、また、この裁判の最初の判決となった杉本判決(昭和45年7月17日東京地裁)にも、多大の影響を与えたと自負している。この判決は、教育内容に関する教育行政権の介入を排斥した。また、その延長線上に位置づけられる学力テスト旭川事件最高裁判決(昭和51年5月21日大法廷)では、「国が教育の大綱的基準を超えて教育内容に介入するのは、憲法26条、13条にも反する」と明言されている。こうして、教科書裁判支援運動や、これらの判決に対するマスコミの解説や講演活動で僕は多忙だった。
憲理研は、創設初期の頃、公法学会に対して、(1)理事の選挙制化と、(2)学会開催テーマへの会員の要望を申し入れたりした。(1)については半数選挙制が、(2)については、会員の要望は複数の分科会を設定することで実現された。
その頃の僕は、形式的には事務局を離れても、憲理研の対外的な交渉役は果たしていた。例えば、全国憲や法社会学会、最も多かったのは東京教育法研究会などとの共同研究会であり、その成果として、「教科書裁判と憲法」なるテーマの共同のシンポジウムを開催したりした。これは法律時報臨時増刊『教科書裁判』(1969年8月)に掲載されている。
以上が、僕の目からみた憲理研創設の頃の状況であった。
[2012年8月28日記]
憲法理論研究会の草創期の想い出
吉田善明(明治大学名誉教授)
(1)それぞれの研究会には、歴史的雰囲気が背景にありますが、それはいつの時代にも生命に充ち、常に新生されるべき場でなければならない、と思っています。それはその会のスタッフ力によるものであるといえます。当「憲法理論研究会」(以下「憲理研」という)は、1964年に設置されました。当時の、まだ若い研究者仲間が、憲法学界の泰斗鈴木安蔵先生を代表に迎えて生まれた研究会でした。大須賀明事務局長(早稲田大)、故影山日出弥氏(名古屋大)、隅野隆徳氏(専修大)を中心に私も事務局の一員として運営に参加しておりました。当時の事務局スタッフ及び協力者のエネルギッシュな活動は大変なものでした。世相の憲法状況が厳しく、とくに改憲論議が活発であり、また、それに対応して学界の憲法学研究の在り様が問われている時でもありました。「憲理研」創立の翌年、各大学の憲法学を代表する研究者が護憲を標榜する『全国憲法研究会』(代表高柳信一東大)を設置したこともあって、責任ある政治的、社会的発言は『全国憲法研究会』の方でとの暗黙の了解のもとで、「憲理研」は『科学的憲法の理論的研究』を中心に研究を進めることが確認されました。
(2)当時の「憲理研」草創期の研究活動に思いを馳せるといろいろな風景が私なりに蘇ってきます。
第1に、「憲理研」の活動を通して憲法学界に多数の友人を得たことです。私にとっては、憲法研究をすすめるに際しての貴重な財産でした。若手研究者は、ある段階までは恩師の下で研究をすることが多く、なかなか他大学との研究者仲間との交流ができませんでした。研究会は会員が一同に会し研究を通して多くの刺激を得る場であることは会の性格上当然ですが、とくに、「憲理研」は、春夏の2回の研究総会のほかに『月例研究会』が組まれていました。毎月の研究会ですので、大須賀事務局長は報告者の依頼に、会場の探しにご苦労されておられました。当時のメンバーへの事務連絡は敬文堂の手を煩わしておりました。現在も心よくご協力をいただいていることに感謝いたしております。
第2に、研究会の雰囲気です。大須賀事務局長は、研究会の中で機会あることに「何を言ってもにらまず、にらまれず」の自由な討議の場であることをモットーにしていることを強調されていました。「学問の自由を憲理研の場で確立すること」でした。実践されていたと思っています。今となっては、当たり前のことかもしれませんが、当時の政治や社会領域でのイデオロギーの深刻な対立、それを投影した学界の状況を念頭においての発言でした。
第3に、合宿です。このところ参加する機会もなくなりましたが、私にとっても楽しみにしている一つでした。都会の喧騒から逃れて、地方での合宿は日頃尊敬している先生や懐かしい友人との再会の場でもありました。夕食後は、夜の更けるのも忘れて語り明かすことも屡でした。地方での護憲活動の難しさなどについて意見を交換する場となることもありました。また当時、合宿にご夫妻参加の呼びかけを申し合わせたことも記憶にあります。事務局メンバーから率先しようと、大須賀夫妻、影山夫妻、遠方地にあって事務局の仕事に積極的に協力されていた山下健次(立命館大)夫妻はお子様づれで、私も妻と参加しました。その後も樋口ご夫妻、永井ご夫妻をはじめ同僚、友人のご夫妻参加もありました。今流でいえば、「憲理研」の人間的『絆』の原点かと思います。
第4に、やや、それますが鈴木安蔵先生との想い出について若干語らせてもらいます。先生とは研究会でいつもお目にかかりながら、個人的に会話をする機会もなくおりましたが、事務局のメンバーであるということで、下馬の先生宅に来るように連絡を受けました。大須賀教授と一緒でした。先生の書斎に通され「憲理研」の未来について語り合ったことが想い出されます。その後、永井憲一先生から鈴木先生が教養部長になられ多忙につき、その間、先生が講義されていた教養部の法学を担当してほしいとの連絡があり、それをお引き受けしたこともあって、先生に接する機会が多くなりました。場所はいつも東急プラザ9階のロシア料理店ロゴスキーでした。法学の講義の状況報告等をすませ、あとは戦前の憲法研究の状況とその厳しさについてご教授を得ておりました。先生の昭和10年前後の憲法の3部作『憲法の歴史的研究』(1933年学芸社)、『比較憲法史』(1935年三笠書房)、『日本憲法学の生誕と発展』(1934年叢文閣)に取り組まなければならなかったこと、「治安維持法違反事件」、「天皇機関説事件」、「2・26事件」、遠くは「自由民権運動」の研究等にも及びました。また、「天皇機関説事件」についてのご教授をいただくなかで、鈴木先生は「吉祥寺の美濃部邸はその後どうなっているのか、あそこで美濃部先生は暴漢に襲われた」(1936・2・21)ことを話されました。「現在、人は住んでおらず、空き家になっています」と返答しますと、先生は「美濃部邸をみたいですね。」と話が発展しました。私の家から2,3分のところですのでぜひ案内させてください、その際、私の家にも是非ということになったことが思い出されます。桜のシーズンが終わり、青葉の頃でした。先生を吉祥寺駅にお迎えし主のいない空き家の庭(現在はマンション)およびその周辺を散策しましたが、先生は、美濃部先生との想い出に耽っておられたのが印象的でした。その後、わが家に案内し、やはり戦前の憲法史の話が続くなかで、「君は、イギリス憲法史の研究に関心を持たれているのだから、日本の憲法史研究も本格的にされてはどうか、君の大学の大先輩に憲政史の研究家である尾佐竹猛先生がおられたのだから大学図書館に豊富な資料があるだろう」といわれ、先生の鋭い激励とも思われる言葉に敬服し聴いておりました。その後、この言葉がいつも私の脳裏にありながらも、本格的な研究の成果もなく今日に至っています。憲法史の研究に偉大な業績を残された先生にお会いできたことは私の研究生活のなかで大変幸せなことでした。
(3)当時の若手研究者で結集する「憲理研」に参加されたメンバーについて一人一人語ることはここではできませんが、何れの先輩、同僚も「憲理研」で鍛えられたメンバーとして、その後の日本の憲法学を堂々と担っております。「憲理研」の研究の重さをひしひしと感じております。最初に提起しましたように「憲理研」は、研究を通して「常に、新生されるべき場である」。憲法科学の課題の追究は、日本の国家、憲法の発展に連なることを確信して研究に専念してください。
[2012年9月4日記]
草創期憲理研の記憶
樋口陽一(東京大学、東北大学名誉教授)
『憲理研30周年のあゆみ 1964-1994』という小冊子に2枚の集合写真がのっていて、「いずれも樋口陽一会員提供」とある。こんどあらためて水島朝穂さんから原画の提供を求められたが、〈3.11〉で「大規模半壊」と認定された仙台自宅の混乱で、そのありかを探すのをあきらめた。おそらく転写したものが今回皆さんに紹介されるだろうが、68年水上合宿から40余年に及ぶ時の流れを思えば、転写を重ねたせいで輪郭のぼやけた画面もそれにふさわしいと言えそうである。(編集部注)
68年の研究合宿は、翌年の「第1回」から恒例化する夏合宿のきっかけとなった。もしそれが無かったとしたら、その後の憲理研の活動のありよう自体も違ったものでしかなかったろう、というほど大事な出来事だったと思う。仙台にいて月例会には出席できなかった私だったが、合宿には比較的多く参加してきた。初期の合宿の雰囲気については、鈴木安蔵先生追悼の文章(『日本憲法科学の曙光』所収)で触れたから、ここではくり返さない。
68-69年といえば、いわゆる大学紛争が最高潮のころである。学生(の最良の部分)と教師(の最良の部分)は真剣に対決し合っていた。学生相互の間でも、教師集団の内部でも、(最良の部分同士かどうかは別として)激しくぶつかっていた。そういう中で、憲法をめぐる議論も、ひたすらに「民主憲法」「平和憲法」を護れという立場から「憲法ナンセンス」を叫ぶ声までが交互していた。
「ブルジョア法学」と「民主主義法学」は、多くの場合、背を向け合ったままでいた。「立憲主義」という言葉が今ほどキーワードになることはなく、それどころか、「あー、美濃部達吉ですか…」といった調子の受けとられ方だった。世の中では、「護憲」と「憲法改悪阻止」という二種類の陣地があって、お互いの間のゆき来は――例外を除いて――無かった。そしてこれらのことは、高度成長の本格化と環境破壊がもたらす猥雑ともいえる混乱と、しかし同時に、「右肩上り」の奇妙な明るい活気の中でのことだった。ここで「右肩上り」とは、金満ニッポンに向けてのそれというだけではなかった。上り坂の上には、多くの人たちがそれぞれ何か新しい社会のありようを映す雲を思い描くことができていたのである。
そういった学界や世間の雰囲気の中で出発した憲理研が、再来年には知命=天命を知る齢に達する。憲理研にとっての「天命」は、もとより憲法「理論」研究の他になく、実際、五十年の間、地道に「天」の命ずるところに従ってきたと言えるだろう。
本の間に挟んであったので偶々いま手にしている、すっかり赤茶けた『憲法理論研究・ニューズ』3・4合併号(1966年9・11月)に、鈴木安蔵先生が「合同研究会の意義」という一文を寄せられておられる(6頁)。直接には憲理研と関西の憲法政治学研究会が合同で研究会を開いたことに触れての文章だが、「遠慮のない意見の交換」、「『地方色』や『学閥』をこえて研究者が自由に語り合う」場の大切さということは、「合同」以前の憲理研そのものについて、何より当てはまることだった。
同じ頃に発足した「全国憲法研究会」は、専門家集団としての自己規定をしながらも、「憲法危うし」という問題意識を社会に訴える性格のものであった。全国憲のほぼひとまわり下の世代を主力とし、会員として助手・大学院生を含む――むしろ中心とする――憲理研は、何より地道に「理論」をやろう、というのが鈴木先生の考えだったと思う。「全国憲では理論研究を十分にやれないだろうから、こちらは月例会で徹底的に議論を」という先生の言葉を、十分に正確にではないがおぼえている。
もとより先生自身の「理論」は、「これまでの形式的な、また小市民的な法学や政治学の立場、方法論を克服」しようという、明確で戦闘的な方向性のものだった。しかし、「実証的に解明する努力をしっかりした理論体系として生かしうるような、きびしい理論的交流」を憲理研に「期待」していた先生にとって、何より大切なのは議論の自由だっただろう。実際、先生の文章がのっているページに先立って、私自身、「ブルジョワ科学」と「民主主義科学」を対置する仕方に異を唱える文章を書いている(3-5頁)。「方法論論議の方法的前提」という大げさな標題で、何とも恥ずかしいほどの生硬な文章なのだが、「科学=実践直結論」を仮想の相手方として、引用をしてはいないがM・ウェーバーを基本枠組とした議論をしていた。
憲理研の自由な雰囲気は、初期の事務局員の責任を担当していた大須賀明、吉田善明、影山日出弥のお三方(この順序で1966~76年の10年間)の運営上の力によるところが大きかったと信じている。とりわけ故・影山さんの存在が別格だった。自分自身は先端的なマルクス主義・国家独占資本主義論を説く一方で、学問上の対話を大切にすることで一貫していたからである。酒杯をとることは一切無かったかわり、コーヒーと煙草で何時間でも若手との議論を厭わなかった。事務局責任者として在任中(1976年8月)急逝されたときの衝撃は、言い尽くせない。抽象次元の方法論では、彼と私と交叉するところはなかった。そうでありながらも、彼の没した翌年の『法律時報』(1977年7月)に影山論文(『法の科学』2号〔1974年〕)の書評といってもよい形式で、議会制民主主義論という場面での二人の間の認識の異同とそれにともなう問題点の所在について書いたのは、彼への感謝と鎮魂の思いをこめてのことだった。草創期憲理研の記憶は、私にとって、写真の画面よりも新鮮である。
《編集部注》これらの生写真は永井憲一元会員より提供され、本ホームページに掲載されています。
[2012年8月30日記]
ホームグラウンドとしての憲理研
辻村みよ子(東北大学大学院法学研究科教授)
1 「憲理研によって、研究者として育てて頂きました・・・」。昨〔2011〕年12月の忘年会のスピーチで、私はこう切り出した。実際、大学院生時代から事務局員・事務局長を務めた時期まで、月例研究会や夏季合宿などには、よく参加した。ほぼ皆勤賞に近かったのではないか、と思う。
とくに、1977―79年度に「参政権論」がテーマとなったときは大学院生と助手の身分であったが、月例研究会と研究総会の両方で「フランスにおける選挙権論の展開」等について報告の機会を得た。大須賀明他編『憲法判例の研究』(1982年、敬文堂)、憲理研編『参政権の研究』(1987年、有斐閣)にも寄稿させて頂き、法律時報での連載や拙著『「権利」としての選挙権』(1989年、勁草書房)にもつながった。私の憲法研究者としての歩みは、憲理研とともにスタートしたといっても過言ではない。
2 当時(1970-80年代)は、もとより女性研究者や女子学生が少ない時代(一橋大学では一学年約800人中女子学生は10人、法学部は200人中2人のみ)で、憲法学界では久保田きぬ子先生などを除き、女性は皆無に近い状態であった。1974年に憲理研の研究会(松下圭一先生の市民自治に関する報告)に最初に出席したとき、傍聴者であるにも拘わらず発言を求めて手を挙げると、司会(針生誠吉先生)が思わず「はい、そこのお嬢さん!」と言われたのを鮮明に記憶している(入会前で、名前をご存じなかったのだから仕方がなかったのだが・・)。子育て時代には、研究会後の酒席でも、「あなたには家庭があるのだから、早くお帰りなさい」とよく言われたものだ。今なら、ジェンダー・バイアスだという話になるが、私の方も、「これから帰っても、子ども達はすでに寝ていますので」と言って遅くまで頑張ることがしばしばであった。大先輩たちの経験談はいつも刺激的で、「職業としての学問」への自覚を強めることができた。事務局員を務めることで学会会場の受付に座る機会が多くなり、「やる気度」を示すことにも役立った。
3 憲法の講義の中でも、憲理研合宿のことはよく話題にした。とくに1980年夏の北海道合宿(洞爺湖温泉泊)で、伊達火力発電所、恵庭事件の野崎牧場、長沼基地などを見学したときは、一生忘れられない経験をさせてもらった。火力発電所建設反対の電気料金不払い運動の結果電気を止められて風力発電で生活していた環境権訴訟原告の高校教師正木さんに会い、自衛隊島松演習場に隣接する野崎牧場で「無罪判決はきわめて残念」とする野崎兄弟の話を聞いた。長沼基地では、自衛隊幹部から、「地元住民の平和的生存権を守り、相互の親睦を深めるために」、積極的に「盆踊り大会」などを企画しているという解説を聞いては、苦笑した。幹部は、「地対空ミサイル(ナイキ・ハーキュリーズ)9基が『主として北よりの方向〔当時の仮想敵国ソ連〕』に向けて設置されています。石狩湾上で迎撃しますが、10基飛来したら対応できないので、是非とも軍事力増強が必要です」と、約30名の憲法学者(深瀬忠一、樋口陽一、山内敏弘先生たち錚々たる専門家)に対して宣わった・・。その後、講義の中でどんな批判論を展開したかは、想像に難くないだろう。
4 憲理研30周年を目前とした1992年10月に、制度改革を行って従来の「事務局責任者体制」から「運営委員長と事務局長」体制に移行し、吉田善明運営委員長のもとで[初代]事務局長に就任した(~1994年)。「憲理研30年のあゆみ(1964-94年)」というパンフレットを作成して、上記北海道合宿の写真や芦部信喜・小林直樹先生たちの寄稿文なども掲載した(別掲の冊子を参照されたい)。創立期の先生たちの憲理研への熱い想いが伝わるとともに、水上合宿(1968年)の写真からは、大先生たち(とくに杉原泰雄・永井憲一・影山日出弥先生たち「黒縁めがね集団」)の若かりし頃の面影がしのばれて興味深い。1994年の夏合宿では、仲地博先生たちのお世話によって始めて沖縄にゆき、当時県議〔現参議院議員〕の糸数慶子さんに平和ガイドをして頂いて、読谷村や普天間基地等を巡ったことも貴重な体験であった。現在20号まで続いている『憲法理論叢書』を敬文堂竹内礼二社長[当時]と竹内基雄現社長のお世話で発刊したのも、この時であった。
5 1990年代からは、アジア諸国(とくに韓国)との学術交流も開始した。1989年に国際憲法学会日本支部主催でアジア憲法シンポジウムを横浜で開催したことも契機となり、1992年9月に植野妙実子事務局責任者のもとで韓国合宿を実施した(その年の学術総会も、議会制民主主義をテーマに、梨花女子大学で開催)。その後も、笹川紀勝運営委員長・石村修事務局長、右崎正博運営委員長・加藤一彦事務局長体制のもとで日韓シンポジウムを開催するなど(2000年8月、2002年12月)、相互交流を続けることができた。
なお、2010年2月に国際憲法学会日本支部と東北大学グローバルCOE「グローバル時代の男女共同参画と多文化共生」との共催で、韓国憲法裁判所の李東洽(Lee Dong-Heub)裁判官を招いて講演会を開催することができたのも、上記1992年韓国合宿の折に憲法裁判所を訪れ、李裁判官が担当者としてお世話して下さったことが縁となった。これも奇偶ではあったが、憲理研の貢献があってのことと、思い知った。
6 2011年12月月例研究会でポジティヴ・アクションについて報告の機会を得たとき、これまで一度も『憲法理論叢書』に論文を寄稿していない、という指摘を受けた。当初から、事務局長や編集委員、編集委員長(憲理研40周年記念号〈第12号・2004年〉では「憲法理論研究会40年小史」を掲載)など、事務方を歴任していたことが理由であると「抗弁」したが、たしかに、1999年に東北大学に移ってからは報告や出席も難しくなり、申し訳ない思いでいた。しかし今でも、憲理研が、研究者としての私のふるさとであり、「道場」であったことにかわりはない。
予断を許さない憲法状況の中で、今後も、若手研究者にとって厳しくも居心地のよいホームグラウンドであり続け、次世代の憲法学界を担う「つわもの」が憲理研からたくさん輩出されることを、心から願っている。
[2012年8月20日記]